一度使うと、本当に便利で必須の設備となるテーブルソー。便利なものほど危険を伴う、これ常識ですよね。そう、テーブルソーには危険がいっぱい。
とは言え、木工三種の神器とも言われるテーブルソーを危険だからと敬遠していても始まりません。テーブルソーは繰り返し加工を精度よく、楽に行うことができます。だから多くの方に挑戦していただきたいです。一方でテーブルソーに挑戦する前には必ず知っておきたい作業安全。このブログでは安全な使い方についてお伝えします。
とは言ってもテーブルソーの使い方を徹底的に網羅するわけではありません。手短に、使い方としてこれだけは絶対に知っておいて!ということだけをお伝えします。
目次
テーブルソーに潜む危険とは
これからお伝えする内容は、私がいろんなミスをした経験から学習し、調べて得たものです。幸いにもけがはしていません。皆さんには危険な目に合っていただきたくないので、最後までそして何度も復習してみてください。
テーブルソーで最も危険なのは、キックバックです。
皆さんご存じの方も多いと思いますが、テーブルソーを始めとした回転系の電動工具にはキックバックという非常に危険な現象が必ず付きまといます。これについては文字では伝わりにくいので、キックバックの発生原理を詳しく述べた動画をご覧ください。
どうやったらキックバックを防げるのか?
上記の動画、一言でまとめるなら
切られた材料はどこかに挟まったり、引っかかったりしてはいけないよ!
ということですね。発生する原理は理解できましたか?原理を理解しても、キックバック発生の条件は無限にあります。つまり、キックバックの発生する個別の場合を全て説明するわけにもいきません。
ここでは通常の使用時、どう力を入れて動かせばいいかを教えます。おそらくあなたはそんなこと習ったことはないはずです。YouTubeなどを見ていると、日本のDIYerの方は誤った使用方法をしていることが本当に多いですから。
正解はあるのか?
少し話は変わりますが、ここ、必ず読んでください。
そもそも今から何を学ぶ必要があるのか、根幹に関わるところです。
先ほど「誤った使用方法」と言いました。
つまりこれは絶対ダメ!というやり方があるということですね。一方で、グレーな場合もあります。本人がキックバックの原理をしっかり理解して、何らかの理由でとったやり方だったらいいかと。
そう、つまり明確な線引きというのは存在せず、全てのやり方は自己責任なのです。これから教えることを守れば絶対安全とも言えません。でも知っていたら安全に作業することができます。知らないより知っていた方がいいです。知っていたとしても、実際やるかどうかはあなた次第です。
少なくとも私の経験から、これだけは必ず頭に入れて欲しい!ということをこれからお伝えします。正しいやり方、間違い、と述べますがあくまで私にとっての正解です。何の保証もしません。責任も取りません。全て自己責任ということをご理解して頂いたら、以下読み進めてください。
間違いから学ぶ力の入れ方
ここで学んで頂くのは力の入れ方です。材料をテーブルソーで送る時の力の入れ方は本当に間違いが多発しています。その間違いをきっかけに正しい力の入れ方を見ていきましょう。
材料を押す場所
最も多い間違いが写真のような材料送りです。刃に対してフェンス側ではなく、フェンスと反対側の材料を押すやり方です。これは絶対にやめてください。

この押し方ですと、刃に材料を押し付ける力となって、材料が”引っかかり”やすくなります。そうです。キックバックは挟まったり引っかかったりしてはいけない!でしたね。
そして運よく引っかからずに材料が切れたとしても、カットされた材はフェンスと刃の間で誰にも押されず支えを失います。数千回転で回っている刃とフェンスの間に、ぴったり同じサイズの木材がただ置かれている。どうです?”挟まれて”いつでも飛んでいく準備が出来ているのと同じです。非常に危険です。
ではどこを押すのか?フェンスと、刃の間の材料を押してください。
最も基本的なことですが、これすら知らずに使っている人が本当に多いです。
さらにビギナーの方に多いのが、このように材料の後ろ側を手で押して、進行方向へ押すことにだけ集中しているということです。

ここで考えたいのは、刃の回転方向です。向かってくる方向に刃は回転していますから、刃の一番奥はテーブルソーから上がってきますね。ということは、進行方向へ押す力だけだと、この上がってくる力に負けて、材料が浮き上がる可能性が高まります。そうなると危険です。
ちょっとくらい浮いてもいいんじゃ?いいえ。”挟まり”ます。
下の図を見てください。立ち位置からみた刃と材料とフェンスの断面図です。少し浮くことを想定しています。少し浮く時、理想的にまっすぐ浮き上がれば問題ありませんね。現実的にそのようなことがおこるでしょうか?そうです。刃が浮き上がる力を発生させているのでそれはありません。
図の左側から上がろうとします。
となると、材料は傾きながら浮くわけです。傾いた場合どうでしょう?フェンスと刃の距離よりも材料の方が大きいです。つまり”挟まりました”。刃の最外径のスピードは170km/hにもなりますから、挟まった瞬間もうあっという間です。事故が起こります。
少しも浮かさずに押すことが必要と分かってもらえたと思います。
材料を押す力の方向
材料を浮かせると危険だということで、テーブルソーのカット時には力を3方向にかけることが必要です。
- フェンスに向かって押す力
- テーブルトップに向かって押す力
- 前に向かって押す力
フェンスに向かって押す力、これは正確なカットに直結しますので必須です。刃とフェンスの間がカット後の寸法そのものですから。フェンスに押し付けて初めて正確な寸法にカットできます。そして、テーブルトップに押し付ける力。これは先ほど述べた通りです。浮き上がってしまっては危険です。最後に前に押す力です。
個人的な感覚でいうと、力の分散は、
- 40%:フェンスに向かって押す力
- 40%:テーブルトップに向かって押す力
- 20%:前に向かって押す力
このくらの感覚です。
そんなに前に押す力が弱かったら切れない!と思った方、もちろん私の感覚なのでズレはあるかもしれませんが、おそらくこういう問題を含んでいるかもしれません。
- 適切な刃数の刃を選んでいない
- 切れなくなった刃を使っている
この二つについては別動画で詳細に内容共有していますから、そちらをご覧ください。
適切な使用でも前に材料が進まない時もある!
前に進める力は20%でいい。つまりほどほど軽くということですが、刃数も適切でテーブルソーもしっかりときれいにしてあり、なんら問題ないのに前に進みにくい時があります。
木は成長過程で内部にひずみが生じています。樹種によってその歪の大きさは様々ですが大なり小なり発生しています。ひずみが大きいとカットしたその直後からひずみが解放されて、木が曲がり始めることもあります。その力で刃や割刃が挟まれて、前進する方向への力が大きく必要になることがあります。
それは木の性質だからそのままより強く押して、前に進めるしか仕方ないのか?
答えはNoです。
前に進めている力が通常より明らかに強く必要になってきた場合、やることはたった一つです。スイッチオフです。前に進めず、後ろへも引かずとにかく静かに刃の回転が止まるのを待ちましょう。そして状況を確認しましょう。切られた後の隙間を見てください。
木の内部応力で進まなくなるのであれば、切れた後の隙間にクサビを打つ。もしくは一度引いてもう一度カットするとひずみは解放されていますから素直にカットできます。ただし、寸法は狂いますから工夫してくださいね。
それでもダメな場合、捻じれてしまっているかもしれません。そういう場合は手鋸やバンドソーで粗く5mmほど大き目にカットしてからテーブルソーで最終的な寸法にカットしましょう。5mm大きくしておけばひずみが解放された時に、挟む相手側が無いので挟まれることが無くなります。
3方向への押し方
では、3方向に押すためにどうすればいいのか?
立ち位置
立ち位置にも気を配ってください。立ち位置も力の入り方に関係します。
キックバックが仮に発生してもヒットしないようにこの刃の後ろは可能であればあけてほしいです。だた危ないからと言ってフェンス側に立ってはいけません。どうしても刃の方向に対して力が入ってしまいます。何よりもフェンスと材料の接触部分が見えないので精度が分かりません。必ずフェンスからみて刃の側に立つようにします。そうすれば自然にフェンス方向に力が入ります。
手で押すのはどうなのか?
よく見かけるのが手でこのように押しているパターンです。もちろんダメではありません。百戦錬磨何度も危ない目に合っていながらも素手が良い場合はそれでもいいです。ただ私は初心者に向けてはおすすめできません。

これだと3方向に押すのは難しいです。大きな合板なんかをカットする時は素手でも大丈夫かと思います。手を置いて3方向にコントロールすればいいです。ただし、手が十分に(10cm以上目安)刃から離れる大きさの材料に限ります。そうでなければプッシュブロック、パッドを使うことをお勧めします。

フェンス方向やテーブルトップ方向への力が入れやすいことに加えて、刃から手が物理的に離れます。もしもキックバックが起きても被害を最小限に抑えることができますのでおすすめです。
私が特にお勧めするのはこのマイクロジグのグリッパーです。これまでたくさんのプッシュブロックを買って試しました。安心感はこれが抜群です。強くお勧めできます。
この持ち手も角度を付けられるようになっています。つまり意識しなくても自然に3方向に力が入るように出来ていますね。

あとはよくありがちなのはこういうパッド類は木くずなど、汚れが付くとグリップを失い、かえって危ないということがあります。その点このグリッパーはアルコールで拭くことでグリップが復活してくれるのがうれしいところです。
そして、この大きさ。最初は大きすぎるかと思いましたが、手全体を隠すように保護してくれるので大きな安心感を得られます。これを買ってから以前のパッドは使わなくなってしまいました。もちろんこのサイズ感でやりにくいモノもあります。適材適所で自分の好みにあったプッシュブロックを使ってください。
プッシュブロックも万能ではない
最後にもう一点だけ付け加えておきます。
長い木を切る時はパッドで押し付けることはやりにくいです。そういう時は手で押すにしても、3方向をきちんと意識してください。右手は下へ押す力と前へ進める力。長い木の時にフェンスに押し付ける力を右手では発生させられないです。やろうとすると木がぐらついて精度が悪くなりますから。なので左手を使って、フェンス側へ押し付けながら、下方向へ押し付けながら進めます。この時、左手を添えたまま前に進めてはいけません。

近くなったら離せばいい、そう思っていても人間はどこかで必ずミスをします。他のことに気を取られることが必ずあります。なので、こうやって左手の位置は出来るだけ動かさないことを習慣にしましょう。ささくれが刺さりそうな荒材なら、指で送りましょう。そして、ブレードからは手を遠ざけましょう。
いかがだったでしょうか。テーブルソーを使うとき、キックバックに注意しながら材料を進める力の入れ方についてお伝えしました。本当はたくさんの個別状況について網羅して全てお伝えするのがイチバンですが、現実的には難しいです。
テーブルソーを使っていて、不安に感じることがあったらこのブログやYouTube動画を何度も繰り返し見ていただくと理解が深まります。また、テーブルソーだけでなく、手で持つ丸鋸でも同じことが言えます。原理原則同じですから、応用してみてください。
木工の技術的なことや道具の選び方使い方など、より深く知りたいと思われる方は是非メンバーシップへのご加入を検討ください。皆さんの疑問質問、詳しくライブ配信でお答えします。今は50名を超えるメンバーの方が木工を楽しむために、オンラインスクールに入ったような感じで学んでいらっしゃいます。いつでも解約できますし、再加入もできます。必要な月だけの加入もできます。木工を楽しみ、レベルアップするためにいかがでしょうか。
そこまでは必要ないと思われる方は、無料のメルマガもあります。初心者の方に基礎的な知識を配信していますので是非購読ください。
最後まで見ていただきましてありがとうございました。ではまた次回!








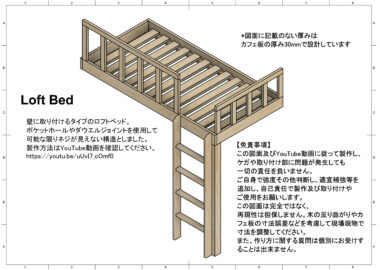



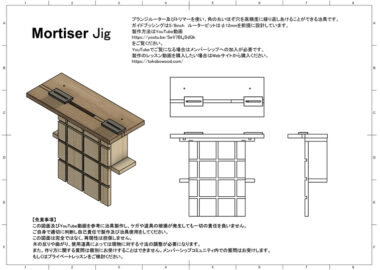






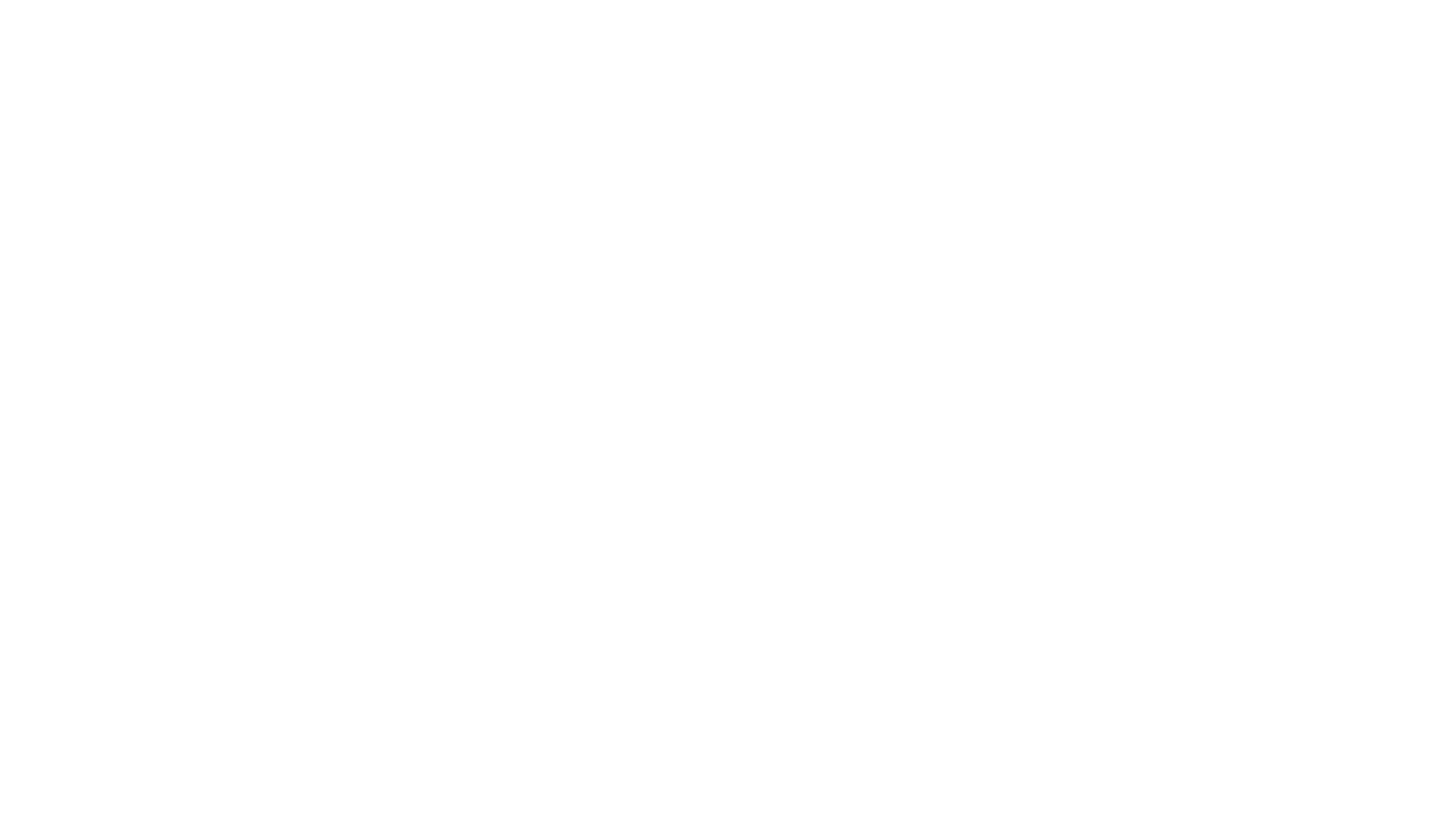
この記事へのコメントはありません。